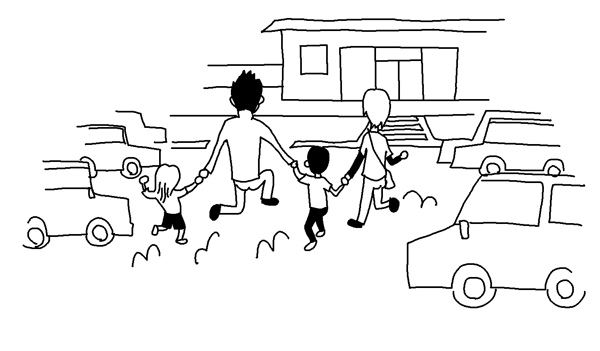問合せ番号:m006
ガソリンスタンドの危機管理マニュアルのカットイラスト
明るい色調で優しい雰囲気のイラストでありながら、
わかりやすい説明にもなっています。



問合せ番号:m006
ガソリンスタンドの危機管理マニュアルのカットイラスト
明るい色調で優しい雰囲気のイラストでありながら、
わかりやすい説明にもなっています。



問合せ番号:m005
小学生向けの防災冊子のためのカットイラスト、その5
「地震発生時の危険な場所(屋内編)」の図

問合せ番号:m004
小学生向けの防災冊子のためのカットイラスト、その4
「地震時の危険な場所(屋外編)」の図

問合せ番号:m003
小学生向けの防災冊子のためのカットイラスト、その3
「図書館は危険!」の図
「家族で避難場所を確認しよう」の図
「運転中も慌てずに」の図
「屋内退避時は食べ物にラップ」の図
「ボンベは元栓を確認」の図



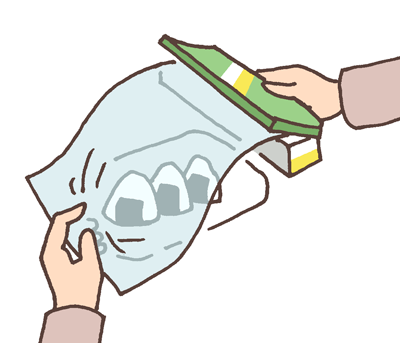

問合せ番号:m002
小学生向けの防災冊子のためのカットイラスト、その2.
「階段ではその場でしゃがもう」の図
「屋外では上からモノが落ちてくるので気をつけよう」の図
「エレベーターでは慌てない!」の図



問合せ番号:m001
小学生向けの防災冊子のためのカットイラスト。
「洪水や床上浸水」の図
「倒れる家具に注意」の図
「キッチンでも慌てず対処」の図



先日、「目につくモノに興味を示す」という娘の習性に気づいたボクは
それを利用して、彼女がなかなか興味を示さなかったキックバイクにまたがらすことに成功した。
久々にキックバイクにまたがった娘は、ほんの数秒でグラグラ不安定なこの乗り物から興味を失ってしまった。
興味を失ったというより、どうしていいかわからなかったんだろう。
またがった、グラグラする、進めない、降りる。
至って自然なプロセスだ。
ふふふ、これでいい。
ボクにはとっておきの「策」があったのだ。
大学や専門学校で20歳前後の若者を教えていて培ったノウハウのひとつ、
必殺!「くりかえす」
僕たち大人でもそうだけど、なんでも繰り返すと結果につながる。
ウォーキングでも、カロリーコントロールでも、早起きでも、ペン字でも
繰り返すことで自分に変化を起こしてくれる。
ちなみに今挙げたモノはすべて最近自分で繰り返してみたもの。
もちろん効果あり。
ってことで、キックバイクを降りた娘にとって大切だったコトは
「明日もまた乗る」ってコト。それだけ。
そして、次の日もその次の日もボクは彼女の目に付くところにキックバイクを設置してから、
彼女を外に連れ出した。
・・・一週間後。
思ったよりずっと早くその時は訪れた。
グラグラを楽しみ、フラフラを怖がらず、ツイツイーと滑るように進む娘の姿。
揺れる、踏ん張る、片方だけ踏ん張ると反対に倒れる、後ろに蹴ると前に進む、足を離すと倒れそうになるが上手く乗れると足を離したまま進む・・
この数日でその身体には様々な経験が蓄積されたはずだ。
たいていの事は繰り返せば身体が無意識に覚える。
楽しくない事は続かない。
まず、楽しめるように工夫する。
楽しいから続く。
そうすると、しらないうちに「出来る」ようになる。
いや、コレほんと。
できない子供たちにガミガミ言う必要はない。
興味が向くように、仕向けて、続くように楽しませてあげたらいい。
そのための知恵を僕たち大人は持っている。
おしまい。
先日イヤイヤ期を終え4歳になった娘は、ちょこちょこ「ガマガマ」をかましてくれるものの、割と平穏な日々が続いている。
「ガマガマ」とは彼女いわく「わがまま」のコトだ。
こう平和になってくると、子供の行動を見守っていても楽しい。
あっちでアレやってたかと思うと、こっちでコレ始めて、もうそっちに移動して、見てる間に散らかり放題・・。
アルゴリズム的に観察してみると、目につくモノに反応して、手にとって、目線が移って、違うモノを見て、またそれを手にとって、の繰り返し。
「!」
ふふふ、久々にひらめきましたよ。
そうか、君、目につくモノに反応するのだね。
ある朝、娘が保育園に行く前のほんの10分、フリーな時間を設けることにした。
そして子供の目につくところに「キックバイク」をさりげなく置いて彼女を外へ誘い出す。
キックバイクとは、子供用のペダル無し自転車のこと。
コレに乗っておくと、補助輪無しの自転車に乗るのが楽だろうと思い、以前与えてみたものの
またがった彼女はいきなりグラグラするこの不安定な乗り物に難色を示し、以来コレに触れることは無かった。
しかし
彼女がそのキックバイクの近くを通り過ぎようとした時、壁をすっていた手がハンドルに当たる、
手が自然にハンドルを握る、
もちろん、彼女の進行方向を予測して設置していたので、あとは足をまたぐだけで乗れるこの上ない体勢、
彼女がコチラを見る、
「のってみよかなぁ」
きた!まさに今、目につくモノに興味を示した彼女はあのキックバイクに再びまたがったのだ!
そして グラグラ、グニャグニャ、グラ〜リ、グララ・・
あ、降りた・・・。
以前、一回だけ乗ってみたあの時と同じだ。
乗ってはみたものの、グラグラして一歩も進まず、降りた。
その間、約30秒・・・。
こうしてせっかくの朝のフリータイム、残り9分30秒はママゴトに終わる。
しかしこの時、ボクにはもう一つ「策」があったのだ。
明けない夜はないんだな。
シェイクスピアばりに劇的な変化が我が家に訪れた。
そう、娘の「イヤイヤ期」が終焉を迎えたのだ。
「魔の2歳」という言葉は知っていた。
しかし、その上位にあたる「地獄の3歳」は知らなかった。
でも、本当にあった。まさに地獄の1年・・。
悪魔の襲来を恐れ、妻と肩を寄せ合って怯えた日々。
様々な貢ぎ物も効果無く、ただただ悪魔のなすがまま・・。
時に顔面を蹴られ、時に仕事の予定を狂わされ、時に息子まで巻き込んで
夜な夜な行われた夫婦国際対策会議も決定的な対策を見つけるに至らず。
身も心も疲れ果て、
いっそこのまま自分も悪魔になってやろうかしら、なんて衝動にも駆られつつ。
引きずり回した日もあった。投げ飛ばした日もあった。
それでも、最後は抱きしめた。
何かメッセージがあるはずだ・・。
ワガママも成長の証だから・・。
大人の都合で考えちゃだめだ・・。
よし、そうだ!ガンバ!マサヒコ!
もっと大きくなってやる!
顔面キックも笑顔で受け止められる大きな大人になってやる!!!
明けない夜はないのだそうです。
ああ、神様、その時が来たようです。
娘が毎日楽しそうに、バッタのように飛び跳ねています。
僕たちを気遣ってくれます。
言うことを聞いてくれます。
もちろん毎回ではありません。
ちっちゃなワガママは健在です。
知ってますか?
ちっちゃなワガママって可愛いんです。 ふふふ。
おしまい。
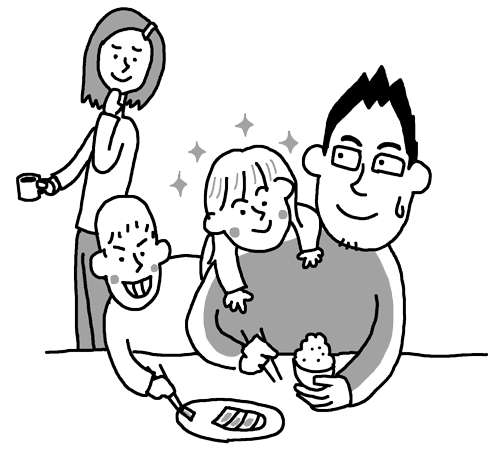
小春日和の休日、近所のショッピングモールに用事があったので家族で出かけた。
本当はどこか屋外で遊べるところへ「おでかけ」したかったんだけど
いろいろ重なってしまい、とにかく買い物だけ済ませるという割と実務的な時間の使い方となった。
屋上駐車場に車を駐めて、エレベーターに向かう。
無駄にぴょんぴょん飛び跳ねる子供たち。
割とよくある光景に
「あぶないよ!、ちゃんと歩きなさい!」
と、言いそうになったけど、な〜んとなく彼らの気持ちを想像してみた。
・・・・
今日はいつもより余計にぴょんぴょんしてる気がする。
何かが、楽しいのか?
楽しくなかったらこんなにぴょんぴょんしないもの・・。
何が楽しいんだ?
屋上駐車場で、せっかくの休みに親の買い物に付き合わされて
おもちゃを買ってもらえる訳でもないのに・・・。
歩きながら、そんなことを妻に話したら、
「そらそうやん、久しぶりに4人で歩いてるんやもん」
!・・・なるほど、「4人で居る」それさえ一つのハッピー。
自分のおもちゃを買いに来たわけでもなく、遊園地に来たわけでもないのに、4人でいるだけでぴょんぴょん跳びはねたくなる。
確かにそんな家族でありたいと思っている。
いや、しかし、ホントにそうなってるんだなぁ・・。
嬉しさと同時にハッとした。
危うく彼らの気持ちに気づかずに「注意」してしまうところだった・・・。
大人から見たら、不用意、不注意、無駄に見える事でも
それは彼らの「こころ」や「きもち」の表れかもしれない。
「不安」「緊張」「満足」「寂しさ」「幸せ」、
彼らは常にいろんなサインをいろんなかたちで出している。
そこに気づけるかどうかって意外と大切なんじゃないだろうか?
「そうかぁ、嬉しいんかぁ」
小春日和の休日、近所のショッピングモールの屋上で、なんだかとっても大きな幸せを感じた。
エレベーターまではもうすぐだったけど、
子供たちの手をとって、ちょっとだけ一緒にぴょんぴょんしてみた。
おしまい。